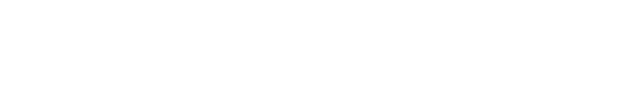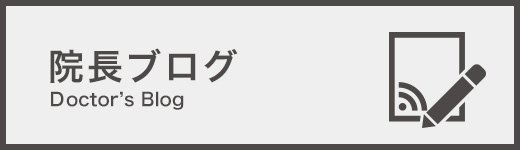【知っておきたい】パーキンソン病とパーキンソン症候群の違い
はじめに
みなさんは「パーキンソン病」という病気の名前を聞いたことがあるかもしれません。手足の震えや動作がゆっくりになるなど、主に高齢者に見られる病気として知られています。しかし、似た症状を示す「パーキンソン症候群」という状態があることはあまり知られていません。この記事では、パーキンソン病とパーキンソン症候群の違いや特徴について、わかりやすく解説していきます。
基礎知識
パーキンソン病とは
パーキンソン病は、脳内の「黒質」という部分にある、「ドパミン」という神経伝達物質を作る神経細胞が減ってしまう病気です。ドパミンは、私たちの体の動きをスムーズにコントロールするために重要な物質です。このドパミンが不足すると、体の動きに様々な異常が現れてきます。
主な症状
1. 振戦:手や足が震える症状です。特に安静にしているときに現れ、何か動作をすると一時的に収まることが特徴です。これを「静止時振戦」と呼びます。
2. 筋強剛:筋肉が硬くなり、関節を動かしにくくなる症状です。医師が患者さんの手足を動かすと、「歯車様固縮」と呼ばれる独特の抵抗感を感じることがあります。
3. 無動・寡動:動作が遅くなり、細かい動きが難しくなります。例えば、ボタンを留めるといった細かい作業が困難になったり、歩く速度が遅くなったりします。
4. 姿勢反射障害:バランスを保つ能力が低下し、転びやすくなります。
原因
パーキンソン病の原因は完全には解明されていませんが、近年の研究により、遺伝的要因と環境要因の相互作用が関与していることが明らかになっています。従来「特発性」とされてきましたが、実際にはさまざまなリスク因子が影響している可能性があります。
- 遺伝的要因:一部のパーキンソン病患者では、LRRK2、PARK7、SNCA、PINK1 などの遺伝子変異が関連していることが報告されています。特に LRRK2 遺伝子変異 は家族性パーキンソン病の原因としてよく知られていますが、孤発例でも関連が指摘されています。
- 環境要因:農薬曝露、溶剤(トリクロロエチレンなど)、重金属(マンガンなど)、頭部外傷 などがパーキンソン病の発症リスクを高める可能性があります。さらに、大気汚染物質(PM2.5など)との関連も研究が進められています。
このように、パーキンソン病は単なる「特発性疾患」ではなく、遺伝・環境要因が複雑に関与する疾患であると考えられています。
パーキンソン症候群とは〜〜〜パーキンソン病との違い
パーキンソン症候群(パーキンソニズム)は、パーキンソン病と似た症状を示すものの、原因が異なる一群の疾患を指します。パーキンソン病は特発性(遺伝・環境要因の関連など原因の特定ができない)のものを指しますが、パーキンソン症候群は明らかな原因があってパーキンソン病に似た症状が出る状態を言います。
パーキンソン症候群の原因とは
| ①薬剤性パーキンソニズム | 抗精神病薬や吐き気止めなど、特定の薬の副作用によって現れるものです。原因となる薬の服用を中止すると、症状は改善することが多いです。 |
| ②血管性パーキンソニズム | 脳の小さな血管が詰まったり、損傷したりすることで起こります。特に下半身の症状が強く、「すくみ足」と呼ばれる歩行障害が特徴的です。 |
| ③進行性核上性麻痺 | 眼球運動の障害や転倒しやすさ、首が後ろに反りやすいといった特徴があります。 |
| ④多系統萎縮症 | パーキンソン症状に加えて、自律神経症状(血圧低下、排尿障害など)や小脳症状(ふらつき、言葉の不明瞭さなど)を伴います。 |
| ⑤レビー小体型認知症 | 認知症の症状とパーキンソン症状が混在し、幻視(実際にはないものが見える)などの特徴的な症状があります。 |
などが挙げられます。その他の原因もあるため、神経内科のクリニックへの受診をお勧めします。当院であれば連携病院へ紹介を行います。
患者さんとご家族のための生活の工夫(パーキンソン病やパーキンソン症候群と診断された場合)
| ①定期的な運動 | ウォーキング、水泳、ヨガなどの運動は、筋力維持や柔軟性向上に役立ちます。特に、LSVT BIG※1と呼ばれるパーキンソン病に特化した運動プログラムは効果的です。 |
| ②転倒予防 | 家の中の障害物を取り除き、必要に応じて手すりを設置するなど、安全な環境づくりを心がけましょう。 |
| ③発声練習 | パーキンソン病では声が小さくなることがあります。LSVT LOUD※2という発声練習プログラムが有効です。 |
| ④規則正しい生活 | 睡眠と食事の時間を規則的にすることで、薬の効果を安定させることができます。 |
| ⑤栄養バランスの良い食事 | 特に、L-ドパを服用している場合、タンパク質の摂取タイミングに注意が必要なことがあります。 |
LSVT BIG:身体の動作を大きくすることを目的とした運動療法です。
LSVT LOUD:大きな声を出すことを意識し、声量と明瞭さを向上させる訓練を行います。
詳しくは神経内科やリハビリテーション専門の施設にご相談ください。
最近の研究と将来の展望
パーキンソン病とパーキンソン症候群に関する研究は日々進んでいます
| ①早期診断マーカーの開発 | 運動症状が現れる前に診断できるバイオマーカー(生物学的指標)の研究が進んでいます。嗅覚の低下、レム睡眠行動障害、便秘などの非運動症状が早期のサインとして注目されています。 |
| ②新しい治療法 | α-シヌクレインというたんぱく質に対する免疫療法(抗体療法)の臨床試験が進行中であり、治療の新たな可能性として注目されています。mRNAワクチンを応用した治療研究もなども進行中。 |
| ③ウェアラブルデバイス | スマートウォッチなどを用いて症状をモニタリングし、より精密な治療調整を行う試みが始まっています。 |
| ④生活習慣の影響 | 運動や食事、睡眠などの生活習慣がパーキンソン病の進行に与える影響についての研究も盛んです。 |
まとめ
パーキンソン病とパーキンソン症候群は、似た症状を示すものの、原因や進行、治療法が異なる疾患群です。早期に適切な診断を受け、専門医の指導のもとで治療を行うことが重要です。また、定期的な運動や生活環境の調整など、日常生活での工夫も症状の管理に役立ちます。
医療の進歩により、パーキンソン病患者さんの生活の質は以前より向上していますが、まだ完治させる方法は見つかっていません。しかし、早期診断技術や新しい治療法の開発など、研究は着実に進んでおり、将来的にはより効果的な対策が可能になることが期待されています。
何か気になる症状がある場合は、ためらわずに神経内科の専門医に相談することをおすすめします。当院は診断・治療のために、連携医療機関へ紹介させて頂きます。早期発見・早期治療が、より良い予後につながります。
本ブログが患者さんのお役に立てれば幸いです。いとう内科クリニック