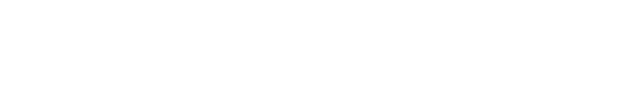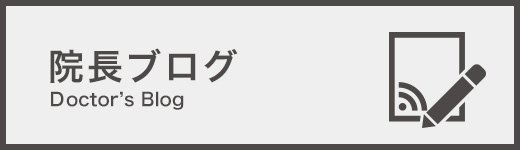心不全の診断・治療
心不全って何が問題なの??
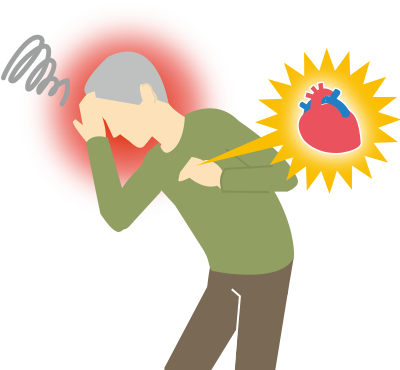
日本における死因別死亡総数の順位では『1位:悪性新生物(がん)2位:心疾患』
これから高齢化が進みどんどん心不全患者が増えてくる『心不全パンデミック』が懸念されています。皆様の健康と生命を守るためにも、症候性心不全に至る前から始める『早期介入・早期治療』がとても重要になります!
心不全を知りましょう!
正しく知って正しく付き合えば怖くない!!
心不全の考え方も少しずつ変わってきています!
最新の定義:『心不全』とは『なんらかの心機能障害、すなわち、心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群と定義される。(参考:2021年JCS/JHFSガイドライン「急性・慢性心不全診療」)
難しいですよね!? もう少しかみ砕いて説明してみます。
心臓と体(各臓器)の関係は車で言うところのエンジン(心臓)と車体(体・臓器)の関係に似ています。車は車体が良くてもエンジンが悪ければ上手に走れないし、エンジンが良くても車体が悪ければ上手に走れません。
心不全は『臨床症候群』=息切れやむくみという症状で判断するので原因が、エンジンなのか車体のどちらにあるかも考えることが必要です。
『代償機転』はしんどくならないようにエンジンと車体がお互いを支え合うイメージです。同じエンジン(心臓)なら元気な車体の方が動きやすいのはなんとなく想像がつきます。
『代償機転が破綻』とは
エンジンも車体も無理をすると壊れますよね?
心臓は頑張り屋さんです!『息切れ・むくみ』といった症状は『そろそろ限界!!』と悲鳴のサインの可能性があります。悲鳴をあげているのに無理をするとバランスが壊れてしまう=『代償機転が破綻』して『心不全の急性増悪』に至ります。
『エンジンと車体の問題を見極めるのが循環器専門医の腕の見せ所です!』
心不全の治療に大事なこと!今の自分を知りましょう!
(参考:急性・慢性心不全診療ガイドライン)
心不全の進展を理解するのに『心不全ステージ分類』があります。
ステージA:基質的心疾患のないリスクステージ
ステージB:基質的心疾患のあるリスクステージ
↓慢性心不全
ステージC:心不全ステージ
ステージD:治療抵抗性心不全ステージ
治療について
心不全の治療・管理は2つの軸が大切です
A:生活習慣 (非薬物治療)
・減塩
・減量
・禁煙
・アルコールの管理
・運動習慣
B:薬物療法
治療薬は心不全の状態によって使い分けが必要です。
降圧薬と一括りにされることもありますが、種類により目的が異なります!
特に心不全患者さんには長期的な目標として『再入院を減らす』ことが挙げられます。
薬はたくさん種類があるので似た働きをする薬でまとめてみます。
①A C E阻害薬/アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)/ARNI
②β遮断薬
③SGLT2阻害薬
④ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)
⑤その他
心不全と付き合うために毎日体重をはかりましょう!!
当院では心不全の自己管理として『毎日の体重測定』を最も重要視しています。
息切れ・むくみなどの症状観察も大事ですが一番大切なのは『毎日の体重測定』です!
理由は『息切れ』『むくみ』などの自覚症状はご本人しかわからない、また症状に慣れていると『こんなもんじゃないの?』と日々を過ごして徐々に悪化していることに気がつかれない方が多くおられます(第一日赤での長年の経験です・・・)。
ご家族様も『自覚症状』なのでご本人が『大丈夫だよ』とお話しされると、『大丈夫かな?』と心配していてもわざわざ病院へ連れて行くのは難しいと思います。
しかし『体重』は数字なので誰がみても管理ができるので、体重が急に増えたら『おかしい』とご家族も気がつくことができ、受診のタイミングを逃さないことに繋がります。
心不全の管理で『体重測定』がなぜ重要なのか。
心不全になると『息切れ』『むくみ』の症状が出てくるのか説明します。
キーワードは『水と塩』です!
⭐︎『元気な人の場合』
僕たちが食べたり飲んだりしたものは、尿・便・汗などの形で排泄されます。
僕たちの体はもともと海から来ている(進化して人間になりました)ので、体の塩分濃度を一定に保とうとする『恒常性の維持』という働きを持っています。
若い時に飲み会に行くといつもよりトイレに行ったことを思い出してください。
- つまみ(塩分多め!)を食べると血中塩分濃度が上昇する→
- 喉がかわく(血中塩分濃度が上昇するので、水で薄めたくなる!!)→
- たくさん水分を摂取する(塩分濃度が下がるので、喉のかわきが改善)→
- 体の水分と塩分が増えているので、バランスをとるため尿で水分と塩分を出します。
- スッキリ!!
⭐︎『心不全患者さんの場合』
1―3までは一緒です。違いは4です!
心臓が弱ると尿が減ってくることが言われています。
尿は腎臓という臓器で作られますが、心臓が弱ると腎臓まで血液が十分に送れないため尿が作りにくくなります(心不全)。
腎臓が弱ると尿がそもそも作れなくなってきます(腎不全)
では『尿が減る』と入ってきた水分はどこに行くでしょうか?
答えは『体』にたまります。
心臓は『筋肉でできたポンプ』なので水分(前負荷)が多すぎると伸びすぎたゴムと同じで縮む働き(心機能)が弱ります。
心臓・腎臓が弱る→尿が減る→水がたまる→心臓がさらに弱る→尿が減る→水がたまる→・・・を繰り返し様々な症状が出てきます。
症状と水分
水分なので体のいろいろなところにたまります。たまった場所によって症状が異なります。
例えば
『むくみ・浮腫』
心不全で足が腫れる・足がむくんでいる患者さんは、足の隙間に水分がたまっている状態ですので腫れているところを押すと押した部位がしっかりへこみます(水分が逃げるため。水なので柔らかいし痛くないことが多いです)。
むくみの場所も、水分なので重力に従って下に降りてくるので足の方が手よりも目立ちます。寝たきりの方だと背中側が浮腫んでいるといったことも多くあります。
『息切れ・呼吸困難』
心不全による息切れ
①胸腔という肺が収まっているスペースがあります。そのスペースに水分がたまります(胸水)。胸水がたまると肺が潰されるので酸素を取り込む働きが弱ります。結果として息切れしやすくなります。
②水分が多いと心臓のポンプに負担がかかりやすくなるので息切れしやすくなります。
※『息切れ』症状の原因はたくさんあります。心不全以外にも『呼吸器疾患』・『貧血』『年齢に伴う生理的変化』なども考慮して判断していきます。
受診の目安
①1週間で3kg程度の体重増加(必須)+②浮腫+③動いた時の息切れ
この3つが揃えば心不全増悪の可能性が高いので早期受診をお勧めします。
逃げ場がないので体にたまります。水がたまるので『体重』がその分増えてくるのです!!
繰り返しますが『体重』は誰でもわかる目安なのでご家族様も管理しやすいのでぜひ協力してあげてください。
知っておこう!心不全の3大原因
心不全を引き起こす3大原因は
①虚血性心疾患 ②高血圧性心疾患 ③弁膜症と言われています。
①虚血性心疾患(冠動脈疾患:狭心症・心筋梗塞等)
心臓の筋肉(心筋)に血液を送る冠状動脈が狭くなったり、塞がったりして、心筋への血液の流れが悪くなり、心筋が酸素不足に陥る状態を指します。
②高血圧性心疾患
長期にわたる高血圧によって心臓の機能に障害が起こっている状態です。
血管に負荷をかけ続けた結果、心筋が肥大してしまうことによる心疾患です。筋トレをイメージするとわかりやすいかもしれませんが、心臓は肥大すると硬くなってしなやかさを失います。そのためふくらんだり縮んだりといったポンプの役割を果たすことが出来なくなります。
③弁膜症
心臓はポンプとして働いているため、入口と出口があります。入口と出口には血液が逆流しないようにふたがあり、このふたのことを「弁」とよんでいます。当然「しなやかに」開閉する必要がありますが、それらの弁が狭窄を起こしたり、閉鎖不全といってしっかり閉じれなくなった状態が弁膜症です。人間の心臓には全部で4つの弁がありそれぞれ「三尖弁」「肺動脈弁」「僧帽弁」「大動脈弁」と呼ばれています。
④その他:心房細動などの不整脈や心筋症も心不全の原因となります
閑話休題
大切な腎臓
尿は『腎臓』という血液ろ過装置で作られます。
腎臓は血液から、水分と老廃物・不要物を取り出して尿を作ってくれます。
→腎臓が悪くなると水分や老廃物がたまってしまい生命に関わってきます(関連リンク:慢性腎臓病・腎代替療法)
心臓が弱っても腎臓が頑張り尿量を維持してくれることも大切です。
心不全の増悪を予防するために循環器内科は腎臓も大切にみています。
最後に
一般的に心臓は取り替えることはできません(移植など一部特殊な状況を除く)。
今の自分の心臓を大事に優しく付き合っていただきたいと思います。
そのために治療の2軸『生活習慣』『薬物療法』を大切にして頂きたいですし、大切にできるようにスタッフ一同サポートしていきます!